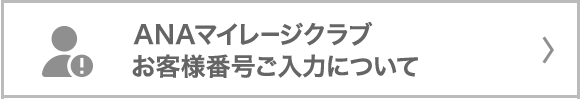【四国八十八ヶ所巡りの入門編】お遍路するなら、やはり車が現実的?おすすめの巡り方を検証してみた!
四国八十八ヶ所巡りのお遍路は世界的に人気上昇中です。その裏付けとして、世界の旅行者に人気な旅行ガイド「ロンリープラネット」で、四国はBest in Travel 2022の地域部門第6位となりました。選出理由は、連綿と続く「お接待」文化のある四国八十八ヶ所巡り-お遍路-が高く評価されたことも大きな一因とのこと。
現在、徒歩の巡礼旅は世界的なブームが起きています。例えば、1993年に世界遺産登録されたスペインのサンティアゴ巡礼路は、1992年には1万人以下だった巡礼者が右肩上がりで増加し、2018年には32万人を超えたそうです。四国八十八ヶ所巡りでも外国人が増加しています。
しかし、世界的に人気上昇中の四国八十八ヶ所巡りも「興味はあるけどよく分からない、実際のところどんなものか、どう巡るのが正解?」と思う方が大多数なのも事実。今回は、入門編としてお伝えいたします。
四国八十八ヶ所巡り-お遍路の歴史と成り立ち

四国八十八ヶ所巡り-お遍路とは、弘法大師(空海)が修行の場とした四国八十八ヶ所に開いたとされる、霊場各所を巡礼する旅をいいます。その歴史を鑑み、文化庁が2015年に日本遺産として登録しました。現在のように八十八ヶ所を巡拝することになったのは、16世紀末から17世紀とのこと。江戸時代初期に、四国遍路ガイドブック『四国遍路道指南』が大衆向けに刊行され、庶民にも関心が高まりました。
空海の足跡をたどる修行の巡礼というだけではなく、庶民の観光という新しい一面が生まれたといえます。現代においては、世代の幅も広く、先祖供養や家族の健康祈願、自分探しのため、または地域観光としてなど、四国八十八ヶ所巡り-お遍路をする目的は人それぞれです。
四国八十八ヶ所巡り-お遍路の巡り方

①四国八十八ヶ所の全体像
四国八十八ヶ所の霊場は四国4県にまたがっており、全行程1,400kmほどです。こちらは北海道県庁から福岡県庁の間の距離1,417.1kmとほぼ同じで、大変な長距離です(国土交通省国土地理院のデータより)。1番から88番まで順番に巡ると、時計回りに徳島県→高知県→愛媛県→香川県の順となります。
各県の様子もそれぞれ特徴があり、以下のようにいわれています。
- ・徳島県(阿波23カ寺)発心の道場
= 思い立ち、行動を起こす(1番~23番札所) - ・高知県(土佐16カ寺)修行の道場
= 精神性を高めるトレーニング(24番~39番札所) - ・愛媛県(伊予26カ寺)菩提の道場
= 煩悩を断ち切り、極楽浄土へと向かう(40番~65番札所) - ・香川県(讃岐23カ寺)涅槃の道場
= 煩悩にうち勝ち、超越した解脱の境地へと向かう(66番~88番札所)
四国八十八ヶ所には、札所間の距離が近くて比較的回りやすい地域や、はたまた次の札所まで数十kmもあって難所ともいえる地域もあります。街中や交通の不便な田園地帯、大変険しい山岳地帯にあるお寺もあり、その道中はバラエティに富んでいます。
②四国八十八ヶ所の巡り方
四国八十八ヶ所の巡り方には特に決まりはありません。時間や体力・ご予算に合わせて、自分のペースで参拝できるのも、四国八十八ヶ所-お遍路の素晴らしい魅力です。なお、お遍路で札所にお参りすることを「打つ」といいます。以下のように、巡り方はさまざまです。現代では、自分のペースで何度かお休みをとり、時間をかけて「区切り打ち」で巡拝する人が圧倒的に多くなっています。
- 1:「順打ち」1番から88番まで順番通りに巡ること。
- 2:「逆打ち」88番から反時計回りに巡ること。うるう年に巡ると3倍の功徳があるそうです。
(逆打ち用の案内表示は設置されておらず、非常に難しいといわれています) - 3:「通し打ち」すべての札所を1度に巡ること。
- 4:「区切り打ち」区間を決め、複数回に分けて巡ること。
- 5:「一国参り」1県ずつ区切り打ちすること。
③四国入りの移動手段
-
1)飛行機
遠方からくる場合、飛行機で四国入りする方が多いと思われます。その場合、徳島空港・高知空港・松山空港・高松空港からとなりますが、1番霊場がある徳島空港から四国入りすることが多いようです。
-
2)車(マイカー)やツアーバスなど
明石海峡大橋やしまなみ海道から車(マイカー)やツアーバスなどで四国入りする方もいます。
④四国八十八ヶ所巡りでの移動手段

-
1)歩き(45~60日前後)(※通し打ちの場合)
空海(弘法大師)の足跡を辿って修行場を巡りたいのであれば、歩きお遍路が一番その大変さを実感できるかもしれません。しかし、通し打ちの場合、1日20~30kmのペースで歩けたとして45~60日間ほど長期間の日程が必要といわれています。そして、天候の悪い時には雨や風に打たれ、まさに辛い修行のよう、かなりの苦行となります。だからこそ、歩きお遍路で通し打ちを達成した時の喜びと満足感は例えようもないといえますが、やはり肉体的ダメージもはかり知れません。
実際のところ、通し打ちを始めた歩きお遍路のうち、最後まで一気に歩き通せるのは3割程度といわれているそうです。また、現代において忙しいお勤めや毎日の家事がある場合、それほどの長期間のお休みをとるのは難しいでしょう。なお、区切り打ちで数回に分けて歩きお遍路するとしても、かなりの覚悟と体力が必要といえます。
-
2)自転車(20~30日前後)
通し打ちの場合、1日50~70kmのペースで輪行できたとして20~30日間ほどの日程が必要といわれています。こちらも歩きお遍路同様、体力勝負といえます。天候の良い時はとても気持ちの良い旅となりますが、天候の悪い場合は雨や風に打たれる苦行となります。
そして、霊場は基本山のため、参道や階段など自転車で行けるところばかりではありません。そんな時には自転車がお荷物になってしまう場合も。しかし、全道程で歩きよりも足の負担は少なく、小回りが利くので自分のペースで回りやすいのが利点といえます。
-
3)車(マイカー)・レンタカー(10日前後)
通し打ちの場合、実際に車で回られた方の平均は10~14日とのこと。やはり、徒歩や自転車よりも体力的にとても楽です。このため、体力の負担が少なく、自由に行動できることが最大の利点でしょう。人によっては、近隣の魅力的な観光地にも立ち寄る方もいらっしゃいます。ただし、四国遍路は高速道路ではなく公道を走ることになるため、思ったより早くは巡れないという声もあります。
-
4)ツアーバス(ツアーコースによる)
体が一番楽であること、詳しいガイドに全てお任せできることが利点でしょう。ただし、団体行動を守らなければならず、長時間において自由に動けないことはストレスとなるでしょう。
-
5)タクシー(予算による)
運転もお任せで、まさにオーダーメードで自分の好きなように巡れるのが利点でしょう。ただし、費用は高額となります。
以上、5つの移動手段のうちから選択されているのは、やはり「車(マイカー)・レンタカー」です。なぜなら、肉体的ダメージも少なく、費用も高額ではなく、なおかつ自由度も高いので、マイカーやレンタカーでお遍路することを実際には選択される方が多いようです。
車(マイカー)でお遍路を巡るメリットとデメリット

車(マイカー)でお遍路を巡るメリットとデメリットを出して、比較してみましょう。
①車でお遍路を巡るメリット
- ・体力的に不安がある人もお遍路ができる
- ・自分たちのペースでお遍路ができる(例えば、観光もコースに組み込む余裕がある)
- ・季節を選ばず、お天気に恵まれなくてもお遍路ができる
- ・大きな荷物でも対応できる
- ・札所付近に宿がなくても、対応しやすい(宿の多い地区に移動可能、または道の駅で車中泊等)
- ・費用をおさえやすい(食費・宿泊費の選択による)
②車でお遍路を巡るデメリット
- ・運転で疲れてしまう
- ・道に迷うこともある
- ・駐車場代やガソリン代がかかる
このようなデメリットもありますが、下準備と心構えをしておけば、かなりカバーできると思われます。やはり、仕事や家庭がある現代人が長期のお休みを取ることも難しく、予定が立てやすく自由に行動できる車を選択することは、一番現実的な選択であると納得がいきます。